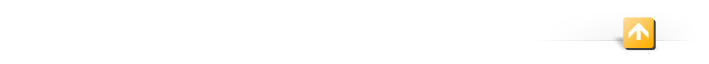多くの場合、社史は編纂前にその発行目的やコンセプト等が検討され、編集作業の大枠が決められます。しかし、それらは概念的であり、かつ抽象的なことが往々にしてあります。 ところが、そのような理念とは別に「できた社史をどのように活用するか、使うか」といった現実的な視点で眺めてみると、意外とユニークで面白い企画が湧いてきます。
1.なぜ目的が必要か?

通常、社史の編纂に際しては2〜3年、場合によってはそれ以上の制作期間が当てられます。そのように長期にわたって編纂業務を行う場合、最初にその制作目 的、すなわちゴールを明確にしておかないと途中で編集方針がぶれることがよくあります。また、途中で企画が腰砕けになってしまう可能性も考えられます。
例えば担当者の交代、経営環境の変化、発言力を持った新役員の就任などさまざまな社内事情がその要因となります。また、確固とした目的がない場合には、実力者から横やりが入ったときに、その人の考え方に左右される結果になりかねません。
つまり、あらゆる状況の変化に対して「この社史はこのような目的で作りますから、その意見は採用できません」という、しっかりした編集上のよりどころが必要なのです。
2.社史の目的とはなにか?
数多くの事例をふまえて、当社では社史の目的(意義)を次の8項目にまとめています。実際には、多くの社史はこれらの目的が複合的に編纂されています。
- 1.経営資料と情報の整理・継承をする
- 2.会社の足跡に学び、今後の経営に役立てる
- 3.会社のアイデンティティを確認する
- 4.社員に周年などの節目を意識してもらう
- 5.社員とその家族に会社への理解を深めてもらう
- 6.業界の内外に感謝の気持ちを伝える
- 7.会社のイメージづくりをする
- 8.社会貢献策の一環とする
またこれらとは別に、次のようなはっきりした目的意識を持って作られたケースもあります。
- ・グループ内の再編を見越して、社内の連帯感を保つためにさまざまな社員参画の企画を盛り込んだ。
- ・町工場からスタートし、上場を視野に入れるまで成長した企業の姿を、次代の社員に伝えるべく人間ドラマとしてまとめた。
- ・ある専門分野で成長した企業の歴史を、業界の歴史として残すために可能なかぎり細目まで記録した。
- ・合併した両社の歴史を相互の社員に知らせて理解を促し、新たな出発の土台作りの一助とした。
- ・周年を記念して会社の企業精神を再確認し、将来に備える糧とした。
3.どのような使い方をするか
ちょっとばかり格式張った「目的」意識とは別に、「できた社史をどう使うか」という現実の視点で考えてみましょう。配布対象者の顔を思い浮かべながら考えると、相手は何を知りたがっているかという視点に立つことができます。すると、どのような内容の社史を作ったらいいのか? ということの解答は意外に簡単に、また必然的に現れてくるはずです。
これを具体的に考えるには、当社の資料「読者設定とその理由」を作成されることで明確にできます。
企業としての資料(記録)を保存して後世に残すわけですから、当然のことですが資料価値のあるものをいろいろな形で網羅することになります。しかも、できるだけ詳細で正確な記述が求められるのはもちろんです。
この場合は、何を資料として重視するかという視点を事前に確認しておくことが重要です。
【重視事項例】
どのようなことを社員に教育するかという目的によって、掲載事項は決まります。企業としての経営理念や思想、企業の伝統や社会に果たしてきた役割、製品開 発の実績、新規事業開拓の足跡、企業合併や提携の経緯、将来の企業像など、会社によって従業員を教育したい目的は異なるでしょう。それを十分に踏まえて、 内容と切り口を吟味することが大切です。
【重視事項例】
- ・経営理念、経営哲学/なぜそのような理念や哲学を持ったかという経緯、背景、創業者の人物像
- ・経営理念が反映された出来事/社内プロジェクト、社会貢献の実績
- ・伝統を物語る出来事
- ・製品開発の物語、秘話、人物伝、会社や社会への貢献
- ・新規事業開拓の物語、時代背景、人物伝、会社や社会への貢献
- ・企業合併や提携等の経緯、苦労の力点、裏話、結果
- ・将来の企業ビジョン/上場、展開
会社としてどのようなことを社会(株主、取引先、消費者等含む)に知ってほしいのか、ということが原点になります。企業としての考え方、企業イメージ、製 品やサービスの特徴や特典、過去の社会貢献活動、業界や消費者に対する啓蒙活動など訴求点を絞って的確な情報提供活動をしてください。
【重視事項例】
- ・企業理念とその展開例
- ・製品開発姿勢とその展開例
- ・これまでの社会貢献活動報告
この場合はどの範囲の誰に配るのかを考えてみると、どのような内容が不可欠か、あるいはあってもいいのかという判断がつきやすいでしょう。まず相手の顔を思い浮かべながら、どのような結果がほしいのか現場の意見をくみ上げて検討してみましょう。
【重視事項例】
- ・幅広い分野からの祝辞
- ・関係官公庁、団体からの称賛の声
- ・優先技術の事例紹介
- ・新製品開発のストーリー紹介
- ・施工事例紹介
- ・使用者(顧客)の声集
- ・アンケート調査の結果解説
4.構成のバリエーション
前付け
口絵
- ・イメージ写真/会社の象徴的なもの
- ・写真で見る歩み/人、モノ、時代背景、事業所紹介
- ・会社の現況/現状、概要
- ・企業環境、社会との関わり/企業活動と社会との関わり
- ・商品、製品、サービスと社会との関わり/モノやサービスと社会貢献
- ・テーマ写真/強調したい業績、プロジェクト、テーマ
本文
- ・企業の足跡/足跡(企業史、経営史、人物史、営業史、技術史、企業文化史、業界史、産業経済史、社会史)
- ・テーマ別の足跡
- ・部門ごとの足跡/事業所、工場
資料編
- ・社内資料
- ・業界資料
- ・年表
後付
上記の一般的な内容に、3項で記した各ケースごとの重視事項を組み合わせて考えてみてください。 伝統のある会社が、とくに商品の変遷を訴求したいのであれば、商品写真やパッケージを年代ごとに並べるのもひとつのやり方です。また、それらの広告活動の推移を紹介する場合には屋外看板の移り変わりを写真で紹介するのも面白いやり方でしょう。
企業としての社会貢献を強調したい場合は、地域との連帯(工場開放や催しものへの協賛)を取り上げるのもひとつの考え方です。
いずれの場合でも、とくに大切なことは大向こうのうけを狙うのではなく、事実をたんたんと正直に記すことです。