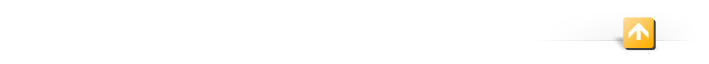社史、年史、記念誌。これらは一体どう違うのかという質問を時々耳にします。実のところ、これらに明確な線引きがあるわけではありません。記念誌のような社史もあれば、社史の形をした記念誌というのもありえます。どこからどこかまでが年史、社史、記念誌という定義はなかなか難しいものがありますが、それぞれの特徴を以下にまとめてみます。
年史という呼び方は、企業、学校法人、市町村などの公共団体、特定の団体の全てにも使用できる言葉です。○○年史、○○周年史という言い方が一般的で、年を区切った周年に出版するという意味合いを強く持ちます。多くはその団体による自主的な記述ですが、歴史的な資料を目的とした第三者の記述による年史も少なくありません。

年史の中でも特に企業が自身の歴史を、内外の資料に基づき客観的にまとめ、自身の責任において出版されたものですが、出版のタイミングとしては○○周年ということには限りません。記念誌と同様、上場や社長交代のタイミングで発刊されることもあります。
社史制作の主な目的としては、企業・団体が歴史を記すということにあります。この「企業」という言葉は法人組織と同じような意義で、NPOなどの非営利団体、財団法人も含まれると考えるのが一般的です。(社史において企業が自主的に自身の歴史をまとめるのは日本の文化であるとされています。諸外国では研究対象として第三者が記述したものが多くみられます)
また社史の中には、以下のような形式が存在します。
- ・正史
- ・略史
- ・編年史
- ・外史
- ・小史
- ・稗史
正しい歴史という意味で、創業前史から発刊タイミングまでの全ての年代を網羅した社史です。通史という表現も同じ意味で使われます。通常はその社史を指して○○正史とは呼ぶことはありませんが、内容の認識として正史であるという位置づけで編集されたものと言えるでしょう。
何度か社史を発刊した場合など、発刊後の歴史を中心にまとめる場合、略史という表現が使われます。たとえば30年史を発刊した経験のある50年の歴史を持つ会社の場合、30年史発刊後の20年分のみをまとめたような社史は、この20年分をきっちり書き、前の30年はダイジェストで書くというケースが多くあります。この場合を略史と言います。また、この略史という言葉には全ての歴史を網羅しないという意味もあります。
一年ごとに歴史をたどりながら追っていく編年体の編集物を指します。
正史の反対の意味で使われます。会社の本社や当局が出版するのではなく、外部のもの、社員達だけで制作する社史を指します。
ある出来事や、イベント、ある特定の人物に関してのみ歴史をまとめる場合、こう呼びます。
事実の確認ができないようなものを集めて歴史書として出版する場合の呼び名です。
周年に限らず、何らかの出来事を記念して出版される印刷物です。この出来事というのは、たとえば新築であったり、関係者の受賞など、もちろん周年記念を含む様々なお祝い事です。出版の目的は記念を寿ぐという意味合いが強く、年史・社史では、必ず歴史記述が入るのに対して、記念誌にはその制約はありません。お祝いと感謝の気持ちを表すということに重点が置かれるため、社史に比べて構成も自由になる傾向があります。歴史記述を含める場合も多くありますが、全体を網羅することは少なく記念的な出来事やイベントを紹介することに重点を置かれています。著名人との対談を入れたり、写真だけで展開する記念誌や、寄せ書き的な記念誌もあります。団体が作ることが多いという傾向もあります。